SNSの普及により、お菓子業界でも美味しいだけでなく、可愛さや写真映えする要素が重要視されるようになりました。
日本では、パンケーキやタピオカ、アイスクリームなど、さまざまなスイーツがブームになってきましたが、忘れてはいけない存在があります。
それが、驚きと美しさを兼ね備えた「ジャパンクオリティ飴」です。
この記事では、「食べられる美の饗宴」として、このジャパンクオリティ飴の魅力を深掘りしていきます。
Contents
可愛くて美味しい!日本の伝統飴が持つ魅力とは?
今回筆者が注目したのは、日本の「飴(あめ)」です。

口寂しい時や仕事の合間のリフレッシュに、老若男女問わず親しまれている飴ですが、この飴にこそ人々を惹きつける日本の魅力がたくさん詰まっているのです。
飴と一言で言っても、様々な日本の飴があるのは皆さんもご存知だと思います。
たとえば、切っても切っても同じ柄が出てくる金太郎飴にしかり。

縁日の定番として知られるリンゴやあんず飴をはじめとする、フルーツをコーティングした飴にしかり。

有名なアニメ映画でも知られるドロップにしかり。

そして数ある日本の飴の中でも、外国人観光客の方々から絶賛されているのが「飴細工」です。
一般的に日本を代表する飴細工は、晒し飴で動物や草花などをかたどり、棒が付いた状態のものをさします。
飴細工の歴史を辿る:平安時代から受け継がれる技術と伝統
そんな飴細工の始まりは平安時代に遡ります。

796年京都に東寺が建立された際、中国から渡ってきた飴職人が供え物として細工した飴を捧げたのが起源であると言われています。
昔は、一日に一斗缶(約18ℓの缶)二缶分の水あめを全て売り物の飴に仕上げることが出来て初めて、一人前の飴職人として認められていました。
しかし、熱い温度の飴をひたすら練って小さい粒に仕上げる飴づくりは大変な重労働で、高齢になるにつれてその作業を続けることが難しくなったため、飴職人たちは歳を重ねるごとに飴を造形する技術を磨き、飴細工を売り歩いて販売することにしたのです。
こうして、江戸時代になると町民文化の繁栄に伴い、飴職人が細工した飴を売り歩く姿が庶民にも身近になっていきました。
当時の飴細工は鳥をかたどったものが多く、江戸時代から昭和の初期まで「飴の鳥」という名で親しまれていました。

この時代の川柳や人形浄瑠璃には数多くの「飴の鳥」に関する記述が残されています。
また、江戸時代後期の戯作者で『東海道中膝栗毛』の作者でも知られる、十返舎一九の『方言修行金草鞋』でも寺の境内で飴細工をつくる男が登場していることから、江戸の人々の娯楽に飴細工は欠かせない存在だったことがわかります。

飴職人の姿は日本だけでなく、海外にも影響を与えていました。
明治初期のアメリカの画家ロバート・フレデリック・ブルームは、日本の人々の様々な生活場面を切り取って描いていますが、そのうちの一つ「飴屋」では、飴職人を取り囲む子どもたちや赤ん坊を背負った女性の姿が美しく描かれていて、とても印象的です。
ロバート・フレデリック・ブルームが来日し描いていた明治初期の日本にも、江戸文化の飴細工は色濃く残っていたようです。

こうした日本の伝統的な飴細工は、手袋を使わず90度くらいまで熱せられた、熱いままの飴を素手と握りばさみで加工していくことでつくり上げられます。
そのため、飴が固まるまでの数分間が勝負。火傷のリスクと常に隣り合わせの中で、美しい造形美が生み出されているのです。
職人の技が光る!飴細工体験で五感を満たす
そんな美しい飴細工を目の前で見て、体験できるのが浅草の花川戸と東京スカイツリーソラマチにお店を構える「アメシン」さんです。
本当に生きているのではないかと思ってしまう金魚や、動物たちの飴細工。
職人技の凝縮された芸術的な作品の数々をぜひ体感してみてください。
公式WEB:浅草 飴細工 アメシン 花川戸店
住所:東京都台東区花川戸2-9-1 堀ビル1F
TEL:080-9373-0644
営業時間:10:30〜18:00
定休日:毎週木曜日(臨時休業有り)
公式WEB:浅草 飴細工 アメシン 東京スカイツリータウン・ソラマチ店
住所:東京都墨田区押上 1丁目1番2号 東京スカイツリータウン・ソラマチ4階 イーストヤード11番地
営業時間:10:00~21:00
定休日:休館日に準ずる(詳しい日程は営業日程をご確認下さい。)
日本の飴の起源に迫る!古代から続く甘味文化の始まり
伝統的な飴細工についてここまでお話してきましたが、そもそも飴はいつから日本にあったのでしょうか。

日本の飴の歴史に迫ります。
飴の調味料としての役割とは?古代から現代までの変遷
かつて飴は調味料の一つとして使用されていました。その歴史は砂糖や蜂蜜よりも古いとされています。
720年に完成した『日本書紀』に神武天皇が大和の国を平定した際に、「大和高尾」の地で「水無飴」を作ったという記載が残されています。

当時は「あめ」ではなく「たがね」という名で通っていたようで、神仏に供えるものとして主に使われ、大変貴重なものでした。
そしてこの時の飴は固形のものではなく水あめだったようです。
平安時代にも飴に関する史実は残されていますが、実際庶民に手の届くものではなく、江戸時代に入ってようやく人々のお菓子として流通するようになりました。
そんな古くから人々の生活に溶け込んでいた飴。日本独自の文化とともに発展してきた飴をここではご紹介します。
千歳飴(ちとせあめ)─長寿を願う七五三の伝統飴─
七五三で幼い子供たちが手に持って写真を撮っている風景。一度は皆さんも見たことがあるのではないでしょうか。千歳飴は元々浅草の浅草寺で江戸時代に発祥したといわれています。

昔は子どもの寿命が短かかったため、紅白の縁起がいい細長い飴は「千歳」という名前とともに長生きを連想させ、親が子の健康と長寿を願う意味が込められており、今日も伝統文化として引き継がれています。
そんな千歳飴ですが、意外と高カロリー!!
更に年齢の数だけ入っている千歳飴を子どもが全部食べるのはなかなか至難の業です。そんな時は、かつて飴が調味料だったことを思い出しながら、溶かして煮物などに使うのも一つの手段です。
千歳飴を使った煮物はコクが出て美味しいみたいですよ。
京飴 ─京都で受け継がれる色彩豊かな伝統菓子─
京都のお菓子と言えば、八つ橋や抹茶のお菓子を連想しがちですが、忘れてはいけないのが「京飴」の存在です。

京飴は京都独自の古来の製法で作られ、砂糖をたくさん使用していながら、繊細で上品な口当たりが病みつきになり、地域ブランド化しています。
またカラフルで見ているだけでも癒されるので、京飴を使った珍しいアクセサリーなども売られています。
京都のお土産の一つに伝統的な京飴を手にしてみるのも新鮮です。
インスタ映え抜群!美味しくて可愛い日本のフォトジェニック飴

今度はインスタ映え間違いなしの今巷で流行のフォトジェニックな飴の世界をご紹介します。飴と共にスイートな写真を撮ってみてくださいね♪
虹色のレインボー綿あめで楽しむ夢のようなスイーツ体験
ザラメを溶かして細い糸状にした、ふわふわの雲のようにファンシーな綿あめ🍬縁日で幼い頃、綿あめをねだった人も多いのではないでしょうか。
そんな懐かしい綿あめがよりおしゃれで可愛くなったのが、TOTTI CANDY FACTORYのレインボー綿あめ。
東京にしか店舗がないにもかかわらず、テレビやSNSでも話題沸騰です!
綿あめの概念を覆すフォトジェニックな綿あめは一度食べてみる価値ありです!
公式WEB:TOTTI CANDY FACTORY 原宿店
住所:東京都渋谷区神宮前1-16-5 RYUアパルトマン2F
TEL: 03-3403-7007
まるで宝石!キラキラ輝くいちご飴の魅力
昔から縁日で一度見つけると買わずにはいられない可愛いいちご飴🍓そんないちご飴の専門店Strawberry fetishが2019年6月に渋谷にオープンしました。
イチゴ好きにはたまらない様々なトッピングを楽しめるいちご飴はもはや宝石を手にしているようなキラキラ感。
どの角度から撮っても映えるいちご飴をぜひ、渋谷で堪能してみてください。
公式WEB:Strawberry fetish
住所:東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109 B2F
TEL:03-3464-0525
定休日:不定休
手土産に最適!喜ばれるジャパンクオリティの美しい飴

日本の飴は、古くから存在する伝統的なお菓子です。
その歴史を受け継ぎながら、飴細工やフォトジェニックな進化系飴など、知られざる魅力が広がっています。筆者自身もその奥深い世界に魅了されました。
外国人だけではなく、私たち日本人も飴の魅力を再認識しながら、ちょっとした手土産やお礼にジャパンクオリティな飴を選んでみるのも粋ではないでしょうか。
執筆:Honami
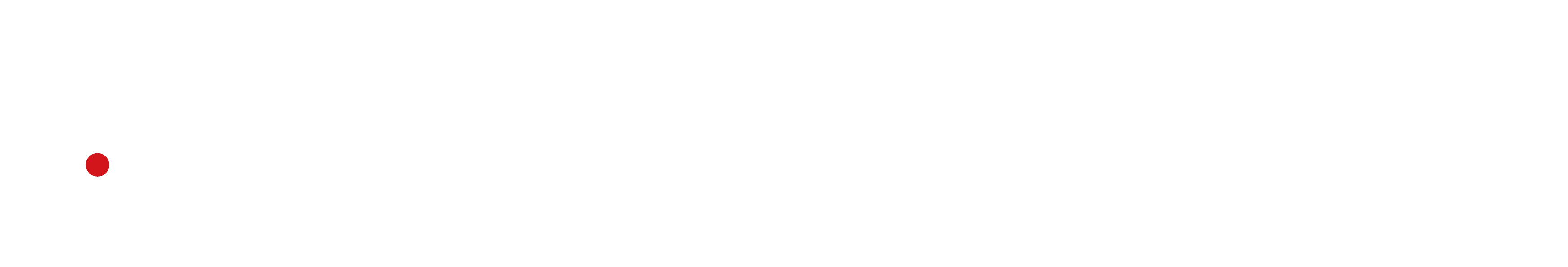






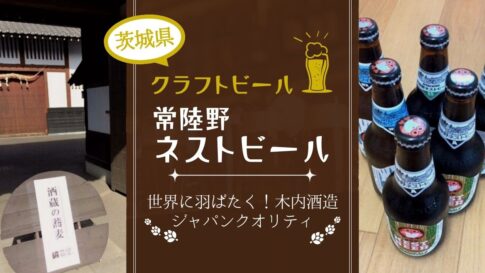





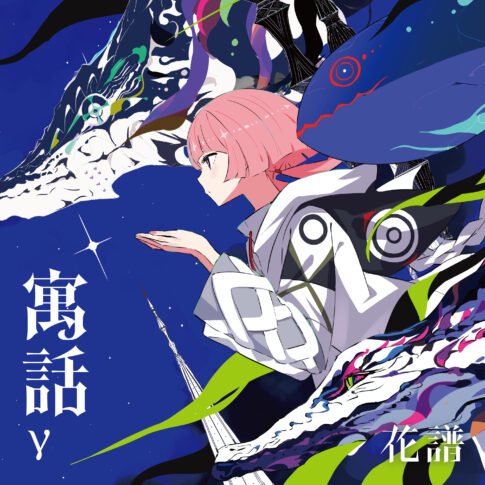







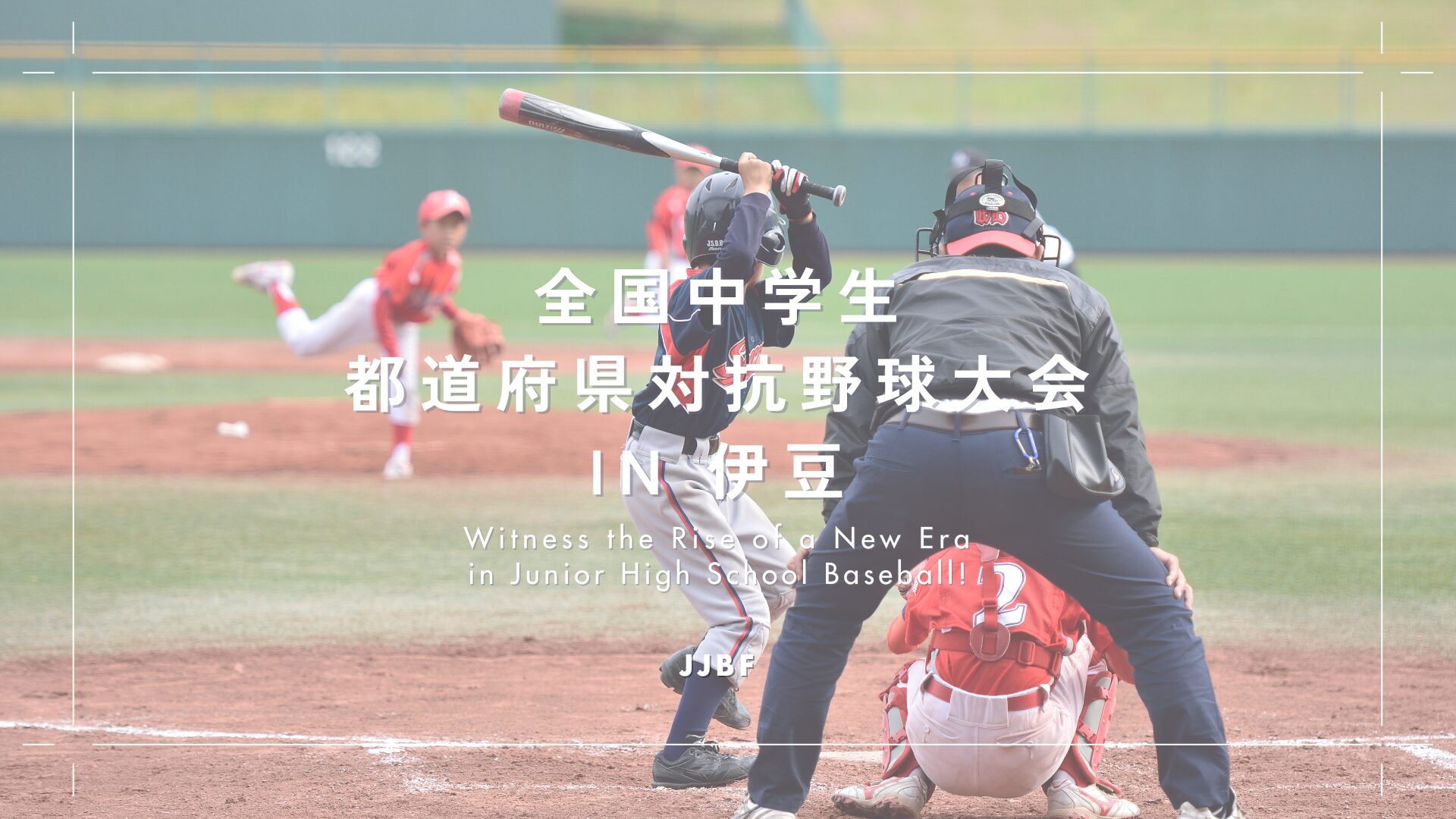
コメントを残す