秋に旬を迎える果物の代表格といえば「りんご」。中でも青森県産のりんごは、みずみずしさ、豊かな甘み、そして芳醇な香りで大変人気です。青森県は、生産量と品質の両方で国内トップクラスを誇り、「日本一のりんご県」として広く知られています。
青森の冷涼な気候と豊かな自然に育まれたりんごは、量だけでなく質の高さも際立っています。多彩な品種と深い味わいが楽しめる青森りんご、その魅力にじっくり触れる機会はありましたでしょうか。
本記事では、青森りんごの栽培の歴史や特徴的な品種、地域ならではの取り組みを紹介し、青森県の風土が生み出すりんごの魅力に迫ります。
Contents
青森が「りんご県」と呼ばれるまでの歴史

まずは青森がりんごの生産量1位になるまでの歴史を辿っていきましょう。歴史を紐解いていくと、青森=りんごの方程式も解明されるはずです。
青森に根付いた西洋りんご
私たちが現在日常的に食べているりんごは「西洋りんご」と呼ばれ、元々は中央アジアの黒海とカスピ海に挟まれたコーカサス地方が原産です。ヨーロッパ経由でアメリカに渡り、明治時代にアメリカから日本に輸入されました。

それまでは、平安時代中期(900年頃)に中国から「林檎」という漢字と共に入ってきた「和りんご」と呼ばれる小ぶりで酸味が強いものが主流だったようです。
さてそんな西洋りんごが青森の土地に根付いたのは明治8年(1875年)春。
米国人宣教師ジョン・イング師により、りんごが西洋りんごとして青森県に紹介され、当時の内務省勧業寮(現在の農林水産省や経済産業省の源流)から3本の苗木が配布されました。
この苗木が県庁構内に植えられたことが、後に青森が「りんご県」と呼ばれるようになる歴史のはじまりです。

同年秋および翌年春の三回にわたって数百本の苗木が配布され、探求心に富んだ農家によって試植されました。北海道から招いたりんご栽培の技術者の指導もあり、この青森の地でりんごの栽培が盛んに行われるようになっていきました。
もちろん、青森の土壌や気候に大変恵まれていたことが、りんご農業の発展の大きな要因であったことは言うまでもありません。
青森りんごを支えた歴史的な人物たち

その土地で発展する農業や産業には、必ず携わった人々の苦労や努力が隠されています。
そこで本記事では、青森のりんご農業に深く関わった人物たちをご紹介し、青森りんごの歴史にさらに踏み込んでいきたいと思います。
青森りんごの父! 菊池楯衛
菊池楯衛(きくちたてえ)1846~1918
青森りんごのパイオニアであり、「青森りんごの父」とも言われる菊池楯衛氏。彼は青森のりんご農業の基礎を築いた重要な人物です。
「りんごを育てる人は、自分に欲を持ってはいけない」
良いりんごを作るためには、人づくりから始めなければならないという信念を持ち、生涯をりんごに捧げました。
菊池氏は津軽藩、現在の弘前市に武家として生まれ、幼少期から勉学に励みながら、植物にも強い関心を示していました。
当時、武士と農工商の身分は厳格に分けられており、武士が農業をすることは禁じられていました。しかし、菊池氏は後に青森県庁に勤務し、そこで「西洋のリンゴは貯蔵すれば一年あまりもつ」という文書に出会います。当時、日本のりんごは貯蔵には不向きでした。
このことに興味を持った菊池氏は、単身で北海道に渡ります。そこで、アメリカ人の農業技師から果樹栽培の技術を学び、りんごの接木(つぎき)や苗木の仕立てに力を入れて研究を重ねました。
青森に帰郷後、東北地方各地を巡りながら、青森県がりんご栽培に適していることを確認します。そして、仲間にりんごの苗木を分け与え、りんご栽培に力を注いでいきました。
菊池氏がりんご栽培の技術や研究成果を惜しみなく教え広めたことで、青森県のりんご農業の礎が築かれていきました。
りんごの神様 外崎嘉七
外崎嘉七(とのさきかしち) 1859~1924
りんごの神様と呼ばれている外崎氏。明治20年ごろから菊池楯衛の指導の下、りんご品評会で3年連続1等を獲得するまでに成長を遂げました。農家出身として初めて指導者となった人物でもあります。
また、病害虫からりんごを守るために、自身のりんごに袋をかけたことで、多くの生産者がその袋かけに倣うようになりました。
さらに、明治の末に大発生したカビが原因で起こる褐班病(かっぱんびょう)を防ぐため、試験場の技師と協同で、ボルドー液(農薬)の散布を採用するなどの功績もあげています。
戦後のりんご園を復興に導いた 澁川傳次郎
澁川傳次郎(しぶかわでんじろう) 1898~1991
第二次世界大戦で荒廃したりんご園を復興へと導いた戦後復興の祖澁川氏。りんご生産者で組織する「青森県りんご協会」を設立しました。
澁川氏は剪定(せんてい:樹木の枝を切り、形を整えたり風通しを良くする作業)の講師として各地を指導し、りんご生産技術の向上に尽力しました。
りんご「ふじ」の普及に貢献した 齋藤昌美
齋藤昌美(さいとうまさみ) 1918~1991
品種「ふじ」の普及に大きく貢献した青森のりんご生産者の一人。青森県では当初「ふじ」は着色があまり優れないことから増殖に踏み切れずにいました。
しかし、齋藤氏は「ふじ」の優位性にいち早く気付き、栽培に着手しました。「ふじ」については後にも触れますが、その特徴としてまずは味の良さと、果肉に蜜が入ることです。
さらに、貯蔵性に優れ、日持ちが良い点も大きな特長です。
「ふじ」以前のりんごは、蜜が入ると果肉が黒く変色したり、柔らかくなってしまったりしていました。しかし、「ふじ」は世界初の、蜜が入りながらも食感が良く、変色しにくいりんごとして誕生したのです。
齋藤氏はそんな「ふじ」の栽培に力を入れ、他の生産者に求められれば、自分の「ふじ」の木から枝を分けていたそうです。
齋藤氏のそのような活躍があり、「ふじ」は日本全国へ、やがては世界へと普及していったのです。
青森県が「日本一のりんご県」へ成長した理由
このように明治から現代に至るまでの長きに渡り、たくさんの人が青森のりんご栽培に力を入れてきました。その結果、青森が「日本一のりんご県」へと発展したのです。
代々受け継がれてきたりんご栽培の技術や伝統は今日の青森を支える大きな柱となっています。

りんご生産量日本一を誇る青森県弘前市。
また、果物の海外輸出量の65%をりんごが占め、そのうちの9割が青森県産です。
そんな青森がりんごの生産量だけでなく、りんごにまつわる他の事項でも日本一であることはあまり知られていないかもしれません。
様々な「りんごにまつわる日本一」をまとめてみました👍
日本最古のりんごの木 (青森県つがる市柏)
日本最古のりんごの木が青森県つがる市にあります。明治11年(1878年)に植樹されたもので、
青森の厳しい風雪にも負けず、樹齢100年以上になるこのりんごの木は青森県の天然記念文化財として指定されています。
日本最古のりんごの木
出典:青森県つがる市公式サイト
青森県指定天然記念文化財(りんご樹)
昭和35年11月11日指定
品種:紅紋2本、祝1本
樹高:7.4メートル
主幹周: 3メートル
樹齢:140年(2018年現在)
生産量:約40箱(7,200個)
日本一長いりんご並木道と五所川原市の赤いりんご
青森県五所川原市内一ツ谷地区に、約1kmの長さで続くりんごの並木道は日本一の長さといわれています。
さらに、この並木道で実をつけるりんごは、五所川原の特産品として知られる皮も花も果肉までも真っ赤なりんご「御所川原」です。世界的にも珍しく、甘酸っぱさがクセになる爽やかなりんごです。
日本唯一のりんご専門試験機関「りんご研究所」 (青森県黒石市)

青森県黒石市にある地方独立行政法人青森県産業技術センター「りんご研究所」は、日本で唯一のりんごの専門試験場として、様々な研究が行われ大きな役割を果たしています。
旧庁舎は「りんご史料館」として一般に公開されています。
りんご研究所
公式WEB:りんご研究所
住所:青森県黒石市大字牡丹平字福民24
電話:0172-52-2331
青森りんごの贅沢な味わい方と楽しみ方
青森のりんごの歴史、そして青森がりんご日本一となった経緯がわかったところで、実際にりんごを思いっきり青森で堪能しちゃいましょう。
もちろん、そのままのりんごも美味しいですが、せっかくなので青森ならではのりんごを使った○○をご紹介したいと思います。
シードルで大人のりんごを味わう 「弘前シードル工房kimori」
りんごを発酵させて作られるりんごのお酒「シードル」。
最近はレストランなどでも日常的に飲むことができ、日本人にも親しまれているお酒かと思います。
そんなシードルを青森のりんごで醸造している弘前シードル工房kimoriへ足を運んでみましょう。
工房の名前「kimori」は、その年の収穫に感謝し、翌年の豊作を願うために収穫の終わったりんごの木にひとつだけ果実を残す「木守り(きもり)」という風習に由来しています。
お酒の弱い人でも気軽に飲めるシードルを通して、青森のりんごの良さを知ってもらい、担い手の少なくなっているりんご農家の後継者育成に力を注ぐべく始まったkimoriのシードルづくり。
kimoriを代表する2種類のシードル、ドライとスイートは、どちらも人工的に炭酸を加えず、タンクを密閉して二次発酵させることで、発酵時に発生する炭酸を自然に果汁に溶け込ませる製法で造られています。
ドライはアルコール度数も高めで辛口なので、お魚料理との相性も抜群。スイートはデザート感覚で飲め、爽やかな甘さを楽しめます。
ぜひ、青森のシードルで大人のためのりんごを味わってみてください🍎
弘前シードル工房kimori
公式WEB:弘前シードル工房kimori
住所:青森県弘前市大字清水富田字寺沢52-3(弘前市りんご公園内)
TEL:0172-88-8936
バラエティに富んだりんご商品をお土産に 青森「A-FACTORY」
青森県産の食材を使った「食」が集結し、シードル工房と市場を兼ね備えた「A-FACTORY」。
シードル工房で造っている、青森県産りんごを使った自家製シードル「アオモリシードル」の醸造工程をガラス越しに見学することができるのも魅力的です。
A-FACTORYでは今まで見たことがなかったような、個性溢れるりんごの加工品も多数販売しています。
たとえばサクサクで病みつきになる「アップルスナック」や新鮮なりんごをそのままフリーズドライして小さいお子さんでも召し上がれる「ソフトりんご」。
高級紅茶とりんごをブレンドした贅沢な「りんご香茶」。
他にも青森の地元の素材を使ったスイーツ店、お土産、ちょっとしたおつまみにぴったりの商品などが目白押しなので、ぜひ青森土産を探しに立ち寄ってみてください。
A-FACTORY
公式WEB:A-FACTORY
住所 :青森県青森市柳川1-4-2
TEL : 017-752-1890
営業時間:
【1F 物販ショップ】 10:00〜18:00
【1F 飲食ショップ)】11:00〜18:00(L.O.17:30)
【2F 飲食ショップ】 11:00〜20:00 (L.O 19:30)
青森県弘前市に行ったら食べたいアップルパイ

りんごの生産量日本一で知られる青森県弘前市は、アップルパイの聖地でもあります。
市内には数えきれないほどのアップルパイが存在し、それぞれお店ごとに全く違った食感や味わいを楽しめます。
そんな弘前でアップルパイの食べ比べツアーをするなら、おすすめしたいのが弘前観光コンベンション協会が発行している「弘前アップルパイガイドマップ」。
市内で販売している41種類のアップルパイを甘味、酸味、シナモンの風味の強弱を1~5段階で表示しながら紹介しています。
またイートインマークも付いているので、その場で食べられるのかお持ち帰りなのかも一目で判断できるアップルパイ好きには堪らないマップです。
ぜひ弘前観光をする際は、こちらのマップを入手してアップルパイを食べ尽くしてくださいね🍎
公益社団法人 弘前観光コンベンション協会
公式WEB:公益社団法人 弘前観光コンベンション協会
住所 :青森県弘前市大字下白銀町2-1 弘前市立観光館内
TEL :0172-35-3131
りんごの驚くべき効果を体験 りんご風呂
イギリスのことわざで「An apple a day keeps the doctor away.(1日1個のりんごは医者を遠ざける)」というものがあるそうです。
世界中で食べられているりんごは、健康食材としての評価がとても高い果物です。
消化が良いだけでなく、解熱・去痰・抗炎症・鎮静・便秘解消などことわざの通り、りんごは私たちの健康に様々な効果をもたらしています。
そして、このりんご食べるだけでなくお風呂に入れても効果があるというのはご存知でしょうか。
青森には、そんなりんご風呂を楽しめる温泉が数多くあるのです。

気になるりんご風呂の効果を見てみましょう。
・血液の流れが良くなり、新陳代謝が高まって、ダイエットの効果がある
・疲労回復や精神安定・リラックス効果がある
・保湿効果や肌荒れの改善に効き、食べるよりも美肌効果がある
・冷え性の改善
お家でりんご風呂を試すのはなかなか難しいと思うので、ぜひ青森の温泉でりんご風呂の効果を体感してみてください👍
知っておきたい!青森りんごの主な品種とその魅力

りんごといっても、様々な種類がたくさんあります。現在世界には約15,000種、日本では約2,000種類のりんごがあります。青森県内では約50種類のりんごが栽培されています。
筆者はいつも購入の際に迷ってしまいます。
そこで、筆者のように迷う方のために、日本でよく食べられている5種類のりんごの特徴を簡単にまとめました。試食や購入時の参考にしていただければと思います。
「ふじ」と「サンふじ」の特徴

青森県りんごの生産量の約5割を占めている「ふじ」。農林省園芸試験場東北支場が育成し、昭和37年に命名、品種登録されました。
蜜入りりんごとして食卓に上がる機会も多いのではないでしょうか。果汁が多くシャキシャキした食感、甘さと酸味のバランスが絶妙です。
「ふじ」は、レッドデリシャスと国光の2種類のりんごを交配して生まれました。赤くきれいな皮にするため、袋をかけて育てられたものが「ふじ」、袋をかけずに無袋栽培で育てられたものが「サンふじ」です。
あまり知られていませんが、「ふじ」と「サンふじ」は実は同じ品種なのです。
「ふじ」は室温で4か月、冷蔵で7か月と貯蔵性が優れています。収穫後は専用の冷蔵庫に保管され、春から夏ごろにかけて販売されます。貯蔵性に優れているからこそ、通年で楽しめるりんごです。
「サンふじ」は太陽をたくさん浴びて育てるため、皮は「ふじ」より色が浅くムラも多いですが、その分蜜が多く入りやすく、糖度が高くなります。
| 「ふじ」収穫時期 | 10月末~11月上旬 |
| 「ふじ」販売時期 | 4月~8月 |
| 「サンふじ」収穫時期 | 11月上旬〜中旬 |
| 「サンふじ」販売時期 | 11月~5月 |
「つがる」の特徴

「つがる」はゴールデンデリシャスと紅玉を交配させたりんごで、青森県りんご試験場が育成し、昭和50年に品種登録されました。
青森で「ふじ」の次に生産量が多いりんごです。
紅色に縞模様が入った鮮やかな色の皮と、シャキシャキ食感とジューシーな果汁、そして酸味をほとんど感じない甘さが特徴のりんごです。
一口かじると、あふれ出る果汁のみずみずしさを実感できます。青森県では「ふじ」に続くほどの高い生産量を誇っています。
| 「つがる」収穫時期 | 9月上旬~中旬 |
| 「つがる」販売時期 | 9月~10月 |
「王林」(おうりん)の特徴

黄色系りんごのパイオニアで、「りんごの中の王様」という意味を込められて名付けられた「王林」。
ゴールデンデリシャスと印度を交配させたりんごで、皮は緑黄色。香りが芳醇で甘みが強いのが特徴です。
果汁が豊富で酸味がほとんどなく、香りが良いので、加工するよりもとにかくそのまま味わうことをおススメする品種です。
酸味を足したい方は、ヨーグルトなどに入れて食べるのも◎
| 「王林」収穫時期 | 10月末~11月上旬 |
| 「王林」販売時期 | 10月末~7月 |
「ジョナゴールド」の特徴

「ジョナゴールド」はゴールデンデリシャスと紅玉を交配させたアメリカ生まれのリンゴです。秋田県果樹試験場が昭和45年日本に導入しました。
「ジョナゴールド」の特徴は、外皮が真っ赤に染まることで、鮮やかな赤に染まっているものが美味しい基準です。また「油あがり」と呼ばれる独特の艶があるので、艶が出ているものも食べ頃と言えます。
他のりんごに比べてやや大きく、酸味が強いのが特徴ですが、その酸味と甘さのバランスが絶妙で、生食はもちろん、ジュースなどの加工品にも適しています。
| 「ジョナゴールド」収穫時期 | 10月中旬 |
| 「ジョナゴールド」販売時期 | 10月中旬~7月 |
「紅玉」(こうぎょく)の特徴

「紅玉」はアメリカ原産のりんごで、明治4年ごろ日本に入ってきました。その名の通り鮮やかな濃い紅色です。
「紅玉」は他のりんごに比べるとカロリーも低く、甘酸っぱさが特徴です。疲労回復や脂肪燃焼に効果的なリンゴ酸が2倍以上あり、健康や美容に効果絶大と言われています。
甘酸っぱさや加熱しても煮崩れしにくいことから、アップルパイなどお菓子作りにも大変適した品種です。
| 「紅玉」収穫時期 | 10月中旬 |
| 「紅玉」販売時期 | 10月中旬~ |
驚きのりんご豆知識でりんご通になろう

とことんりんごに向き合ってきたので、最後にこれだけ知っていればりんごのうんちくが語れるかも✨というりんごのちょっとした豆知識をご紹介します。
筆者はどれも目からうろこの情報だったので、皆さんの話しのネタになれば幸いです。
りんごは皮つきで食べるべし
ついついりんごの皮を剥きたくなってしまいますが、実は皮を剥くという行為は、相当損をしていることをご存知でしょうか?
なぜなら、前述したりんごの体に及ぼす効果や効能は、皮と実の間に豊富に含まれているからです。
そのため、りんごツウの食べ方はこのように輪切りにすること!

輪切りは皮が気になる方もスナック感覚で食べられるだけでなく、芯の部分だけ廃棄になるのでゴミも少なくなって一石二鳥なんだとか👍
りんごとバナナを一緒にすると大変なことに…
りんごには特殊なエチレンガスが含まれていて、このガスはある意味成長ホルモンのような役割を果たしています。

そのため、バナナやキウイなど他の果物と一緒に保存すると、一気に熟してしまいます。
熟していないものに関しては有難いことかもしれませんが、野菜などの足を早めてしまうので冷蔵庫への袋なしの保管は危険です。
一方で、じゃがいも×りんごは、りんごがじゃがいもの有毒な発芽を抑える効果があり、ケーキ×りんごでは、次の日もしっとりふわふわのケーキを楽しめるという逆の効果も…
このように、りんごと相性の良い食材を一緒に密閉して保存しておくと、とても便利なのでぜひ試してみてください👍
世界に存在するりんごはなんと15,000種類
上記でもふれましたが、現在世界中にりんごは15,000種類あると言われています。数を聞いただけでも驚きますが、その内日本で栽培されているのは約2,000種類。

青森県では、現在その2,000種類の中から約50種類のりんごが栽培されています。その中から約40種類のりんごが市場に出荷されています。
青森県では皆さんに1年中美味しいりんごを楽しんでもらえるように、8月から11月ごろにかけて収穫期を迎える品種が中心に栽培されています。
青森りんごを一年中楽しめる「CA貯蔵」の秘密!
今の時代は青森のりんごを一年中楽しむことができます。秋に取れたりんごが一年中楽しめるその秘密は、貯蔵性の高い高品質なりんごの品種改良や、栽培技術の成長、そして「CA(シーエイ)貯蔵」と呼ばれる特殊冷蔵技術にあります。

CA貯蔵(Controlled Atmosphere:空気調整)は果実や野菜の貯蔵法の一種。 酸素を減らして二酸化炭素を増やすように空気の調整と、とさらに温度も低く調整することにより、鮮度を保ったまま長期間の貯蔵を可能にする技術。
収穫後のりんごや果実、野菜は空気中の酸素を必要として呼吸します。しかしこれによって糖や酸が消耗されてしまい、段々と味や鮮度の劣化が進んでしまいます。
空気の調整と温度を低くすることによって、収穫後のりんごの呼吸作用を抑制し、普通の冷蔵保存などよりも鮮度を新鮮に保ったまま、貯蔵期間を大幅に伸ばすことができるようになりました。
青森県では収穫後のりんごを貯蔵時期により「普通冷蔵庫」と「CA冷蔵庫」を使い分けられています。収穫してから3月ごろまでは温度は0℃、湿度は90%前後の「普通冷蔵庫」で貯蔵管理しながら出荷されています。
4月頃から出荷、販売されるりんごは収穫直後から3月末まで「CA冷蔵庫」で密閉貯蔵されています。これによってりんごの鮮度を保ったまま、普通冷蔵庫で保存する通常のなんと約二倍の長期保存が可能になります。
この特殊な冷蔵方法でりんごが眠ったまま新鮮な状態を保ち、青森から全国各地・世界中へと1年を通して出荷されています。
広がる可能性!青森りんごの楽しみ方は無限大

りんごは、果物の定番とも言える存在です。
しかし、その背後には驚くべき歴史や作り手の苦労が隠されています。
本特集では、青森のりんごの世界に少しでもお近づきいただき、青森観光の際には、りんごの魅力を存分に味わっていただければと思います。青森のりんご特集を通じて、青森県の魅力とりんごの素晴らしさをお伝えできたなら嬉しい限りです。
青森おすすめ記事
執筆:Honami
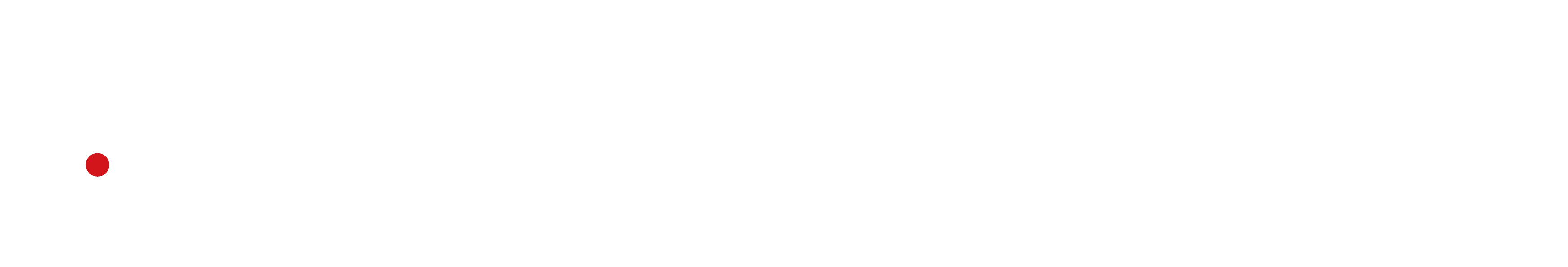












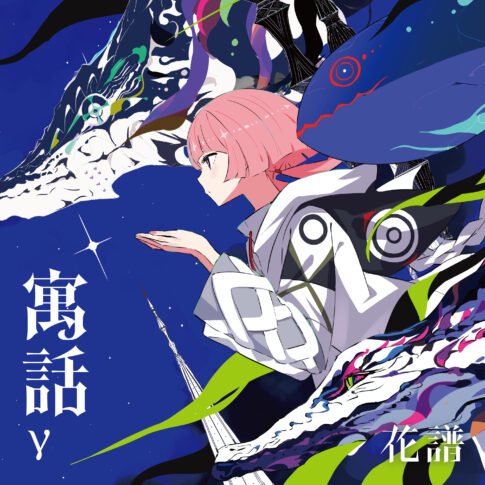







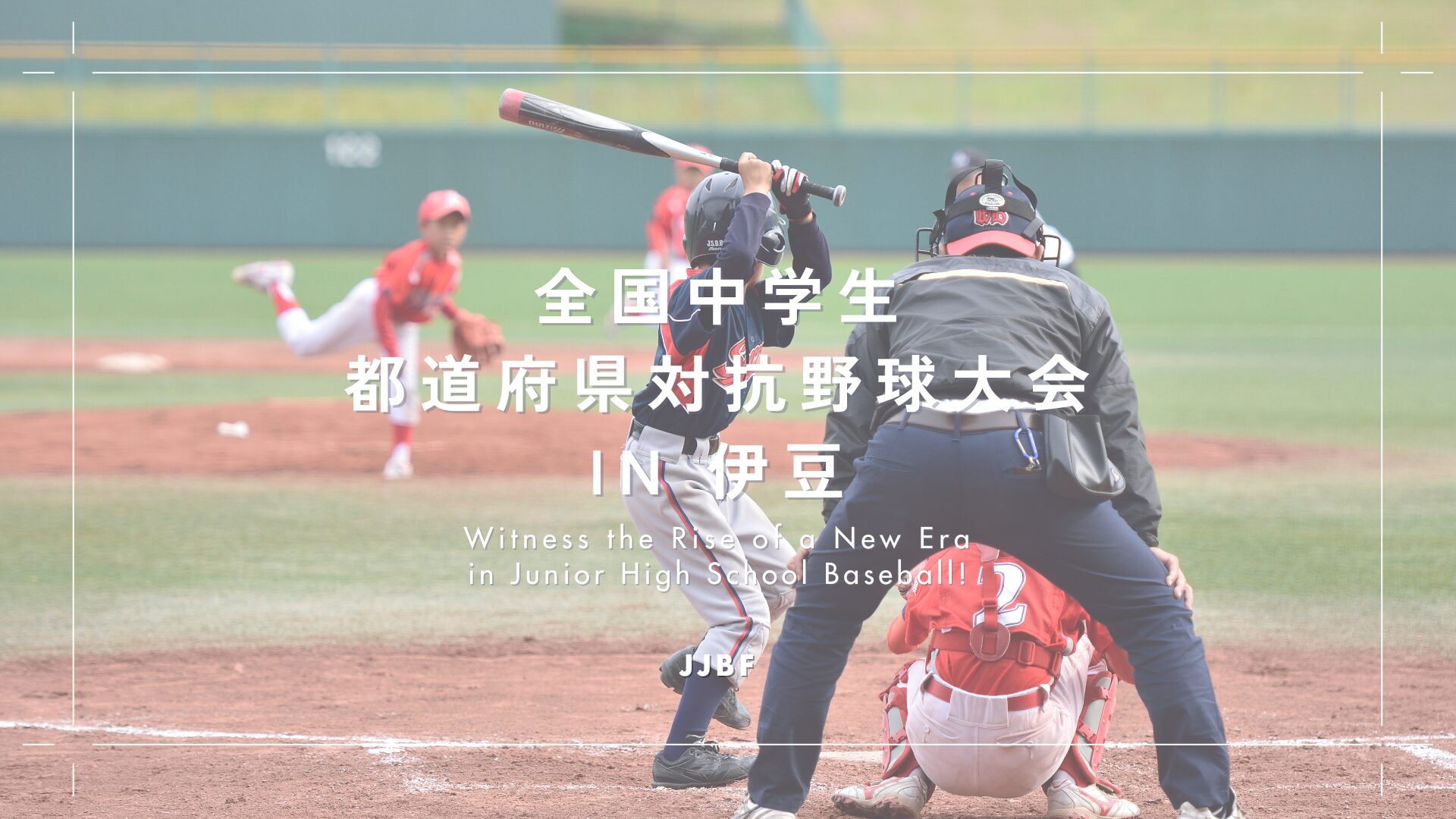
コメントを残す